 Masa
Masa



鉛筆画を中心に作品制作しています。
今回は、
初心者・鉛筆の描き方(鉄則3か条)
「美のカケラ」
| 鉛筆の美しい色と、鉛筆ならではのマチエールを使って、深みのある光の流れや美しい質感を表現しよう。新たな鉛筆表現の世界へ! |
私のお勧めする、描き方は、
こすらない・丸めない・寝かさない
鉛筆は、画面を指等を使ってこすらない。
鉛筆は、丸まってきたらすぐに交換する。
鉛筆は、なるべく立てて描き、寝かせたりして描かない。
-300x169.jpg)
-300x169.jpg)











-248x300.jpg)
-248x300.jpg)
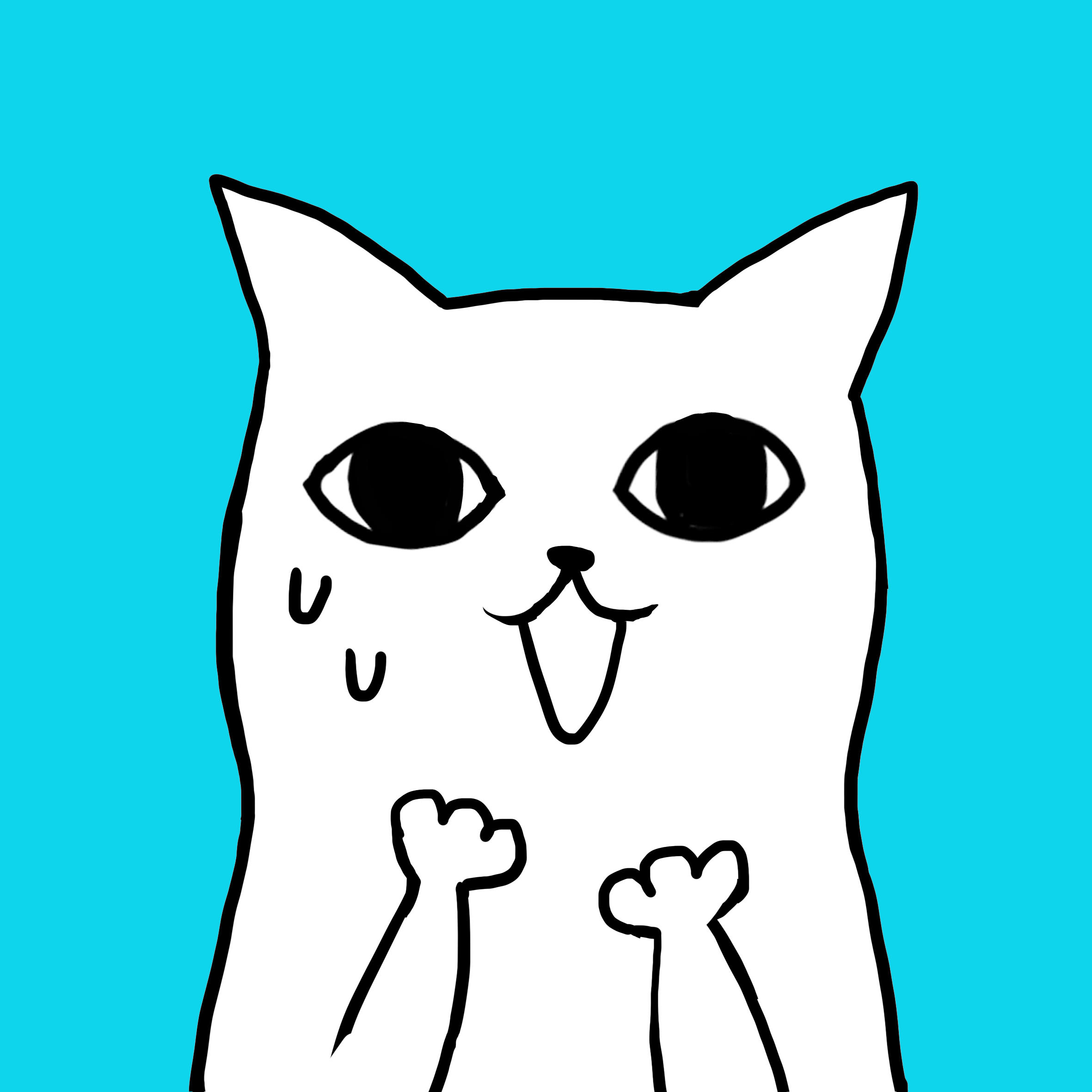
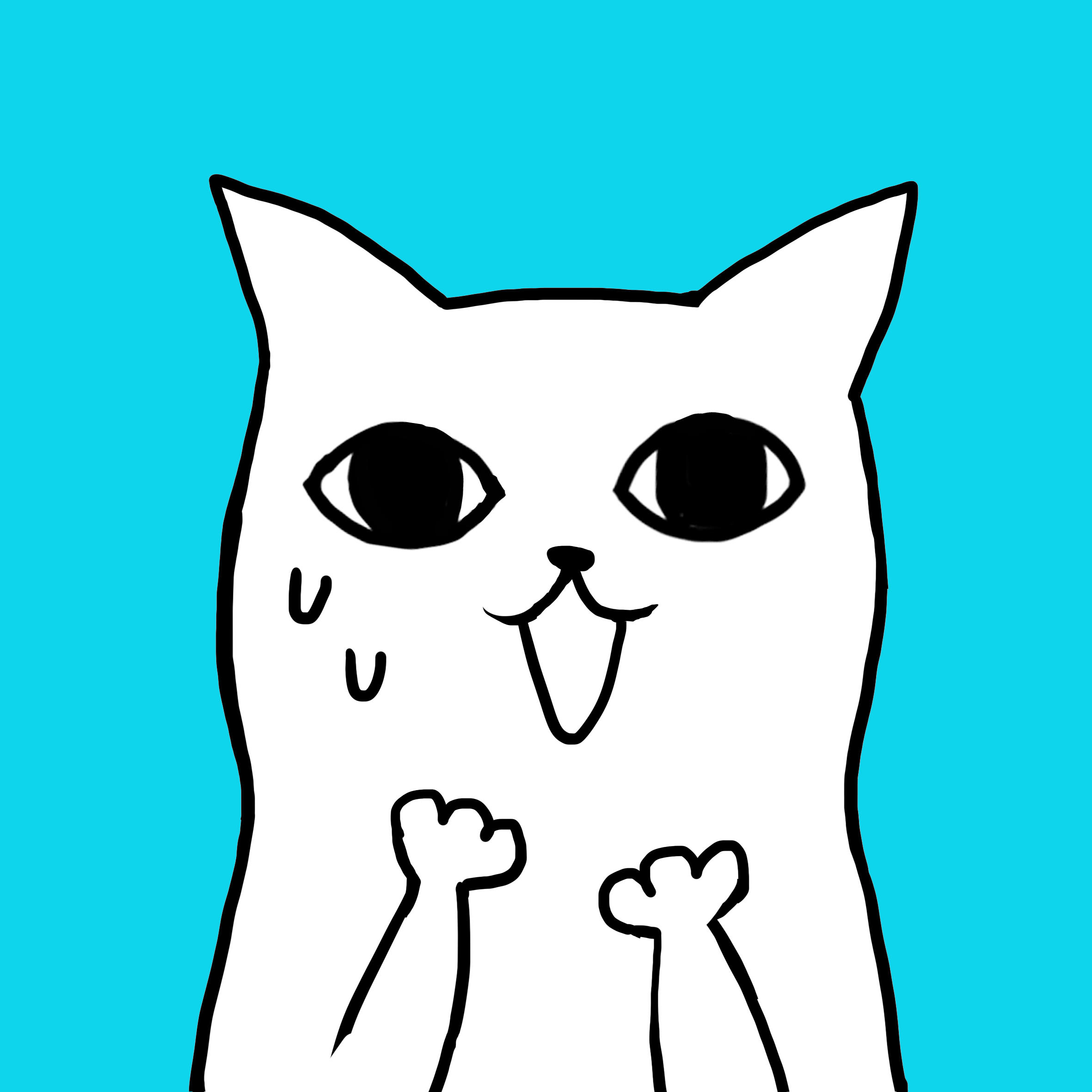
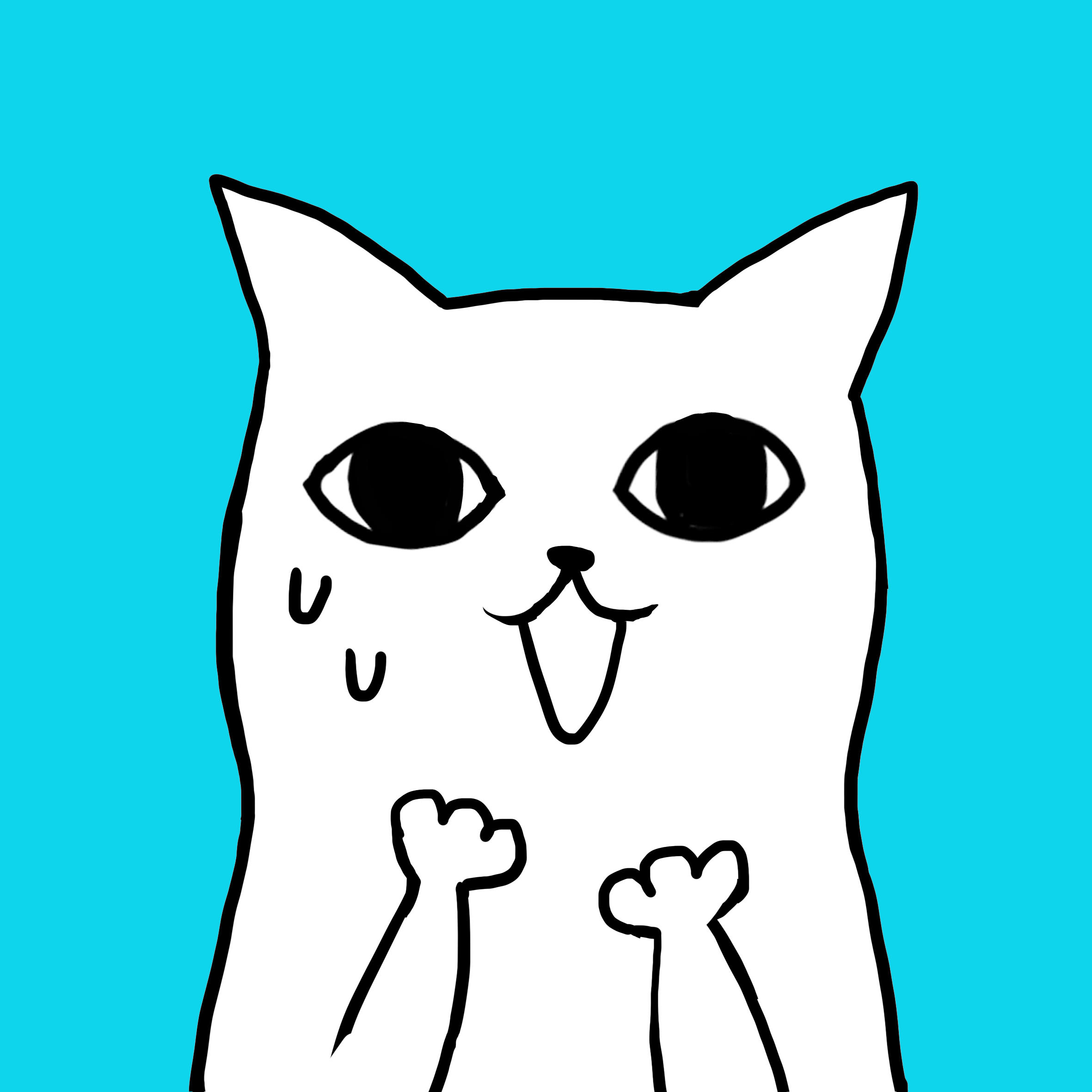
木炭デッサンを描く際には、
木炭の粉が木炭紙によく入り込んで定着するように、
画面を指やガーゼ等を使って、粉を擦り込んだりします。
鉛筆も木炭の一種(黒鉛)だからと言って、
紙に粉を擦り込んでしまうと、
汚れたように見えてしまいます。
鉛筆は、黒という強い色であり、
透明感のない細かい粒子でできていて、
紙の繊維にすぐに入り込み、
風やこすれですぐに飛散し、分散していきます。
もちろん、擦り込むことによる効果を巧みに使う人もいますが、
コントロールが難しく、汚れやすくなるので注意が必要です。
今回の描き方で面を描く場合、
鉛筆の線を何本も引いて面を作るようにしていきます。
濃淡などの描き分けは、
鉛筆の筆圧のコントロールと、
重ねる回数によって描き分けていきます。
1本1本の線をコントロールしながら面にしていくと、
鉛筆の線によるマチエールが生まれます。
このマチエールを利用することで、
描画の表現の幅が広がり、
かつ、綺麗に仕上がると思います。


(線の重ね合わせを変えることで、質感を変えていきます。)
これは好みにもよりますが、
こすることによって描いた面だと、
どうしても存在感の少ない印象になります。
テーマやコンセプトを強く伝えるための工夫としても、
鉛筆のマチエールは有効だと思います。
鉛筆は、どんなに尖らせていても、
描いていくうちに丸まっていきます。
その丸まったままの芯先で描き続けると、
細やかな表現が難しくなり、
コントロールも大まかになってしまいます。
また、
丸まった芯先で描くと、
紙をこすることと同じになるので、
鉛筆独自の綺麗な色が出にくくなります。
なるべくたくさんの尖らせた鉛筆を用意して、
頻繁に交換しながら描いていきましょう。


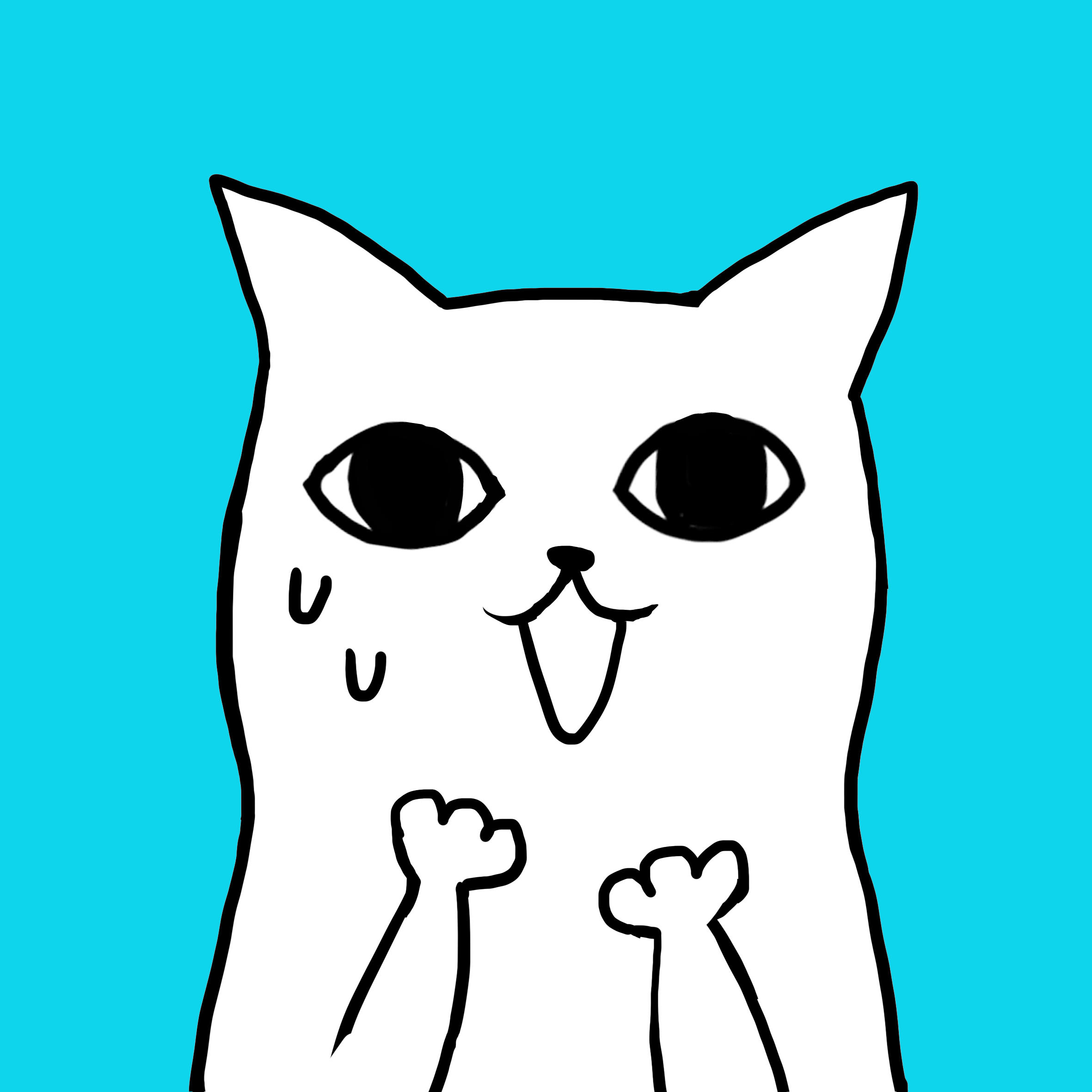
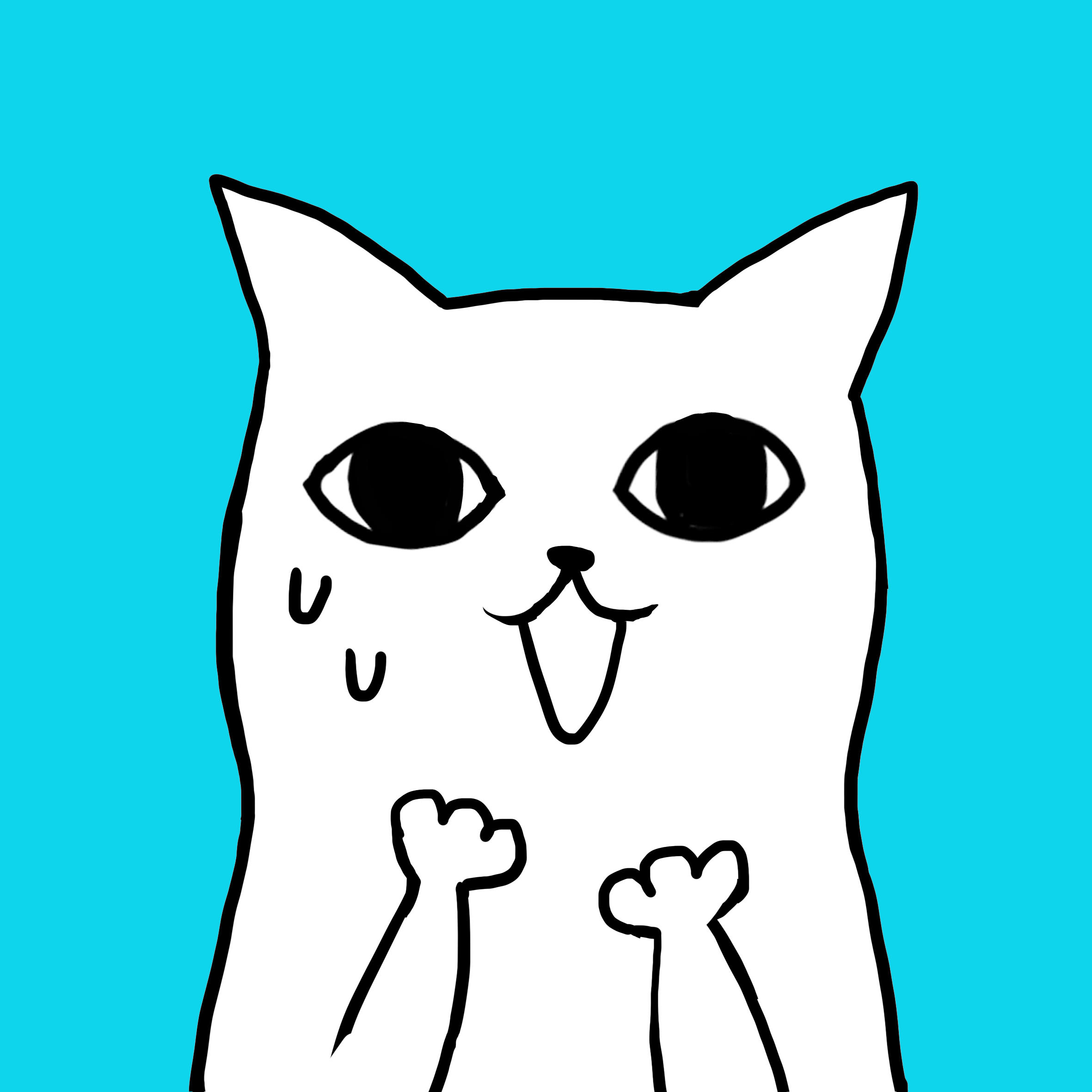
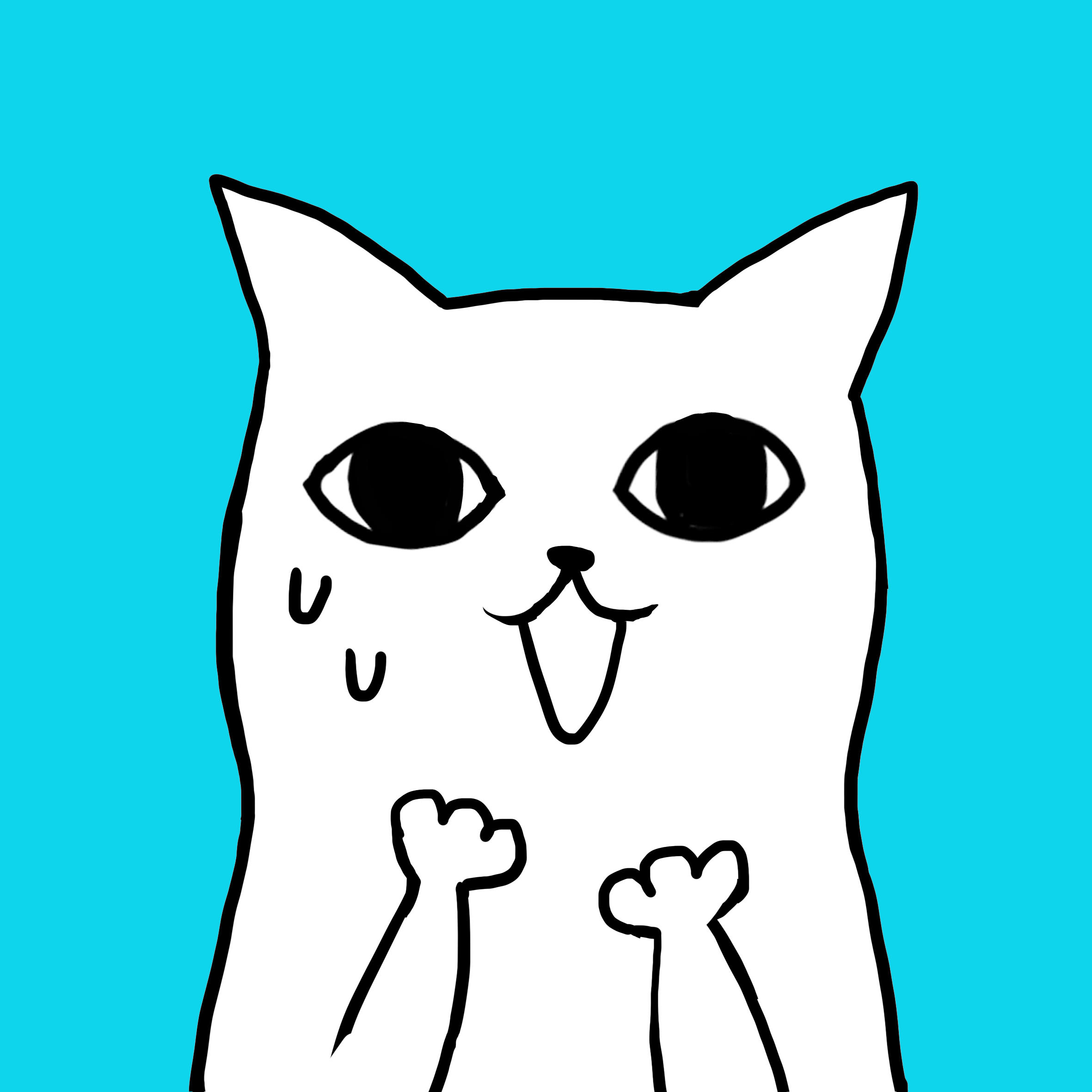



芯先を尖らせた鉛筆は、斜めにして描くと、
すぐにポキッ!と折れてしまいます。
この先端を鋭く尖らせて描く方法は、
元々、斜めにして描くことを想定していません。
しっかりと、立てて描きます。
立てながら力の入れ加減を調整することで、
薄い色から濃い色まで幅広く表現できます。
慣れないうちは、コントロールがしにくいと感じるかもしれませんが、
練習することで、意外と早く身につけることができます。


(鉛筆の線を生かして描いていきます)
「練習方法」については、引き続き、次の記事でご紹介します。
鉛筆は、芯から細かい粉がほぐれて、紙などに色が移ります。
気をつけないと、その粉が手や服に付着し、
絵を汚してしまう可能性があるので、
十分に気をつける必要があります。
紙面の上に残った余分な鉛筆の粉は、
取りたい部分のすぐ横に、
汚したくない部分を紙でカバーしてから取るようにします。
取る方法は、
スポイトの風で吹き飛ばしたり、


柔らかな筆で、そっと取り去るようにしましょう。
筆の場合は、同じ場所は2回以上履かないようにし、
また、同じ方向へ履きます。
こうすることで、汚れを最小限にでき、
かつ、残している白い部分を保護できます。


汚れに注意し余分な粉を排除していても、
描き進めるうちに、
白く残した部分(ハイライト)に、
うっすらと粉が覆い、灰色がかってきます。
ある程度描き進めた段階で、
周りとの調子を見ながら、
消しゴムで綺麗に取り去りましょう。


テンプレートなどを使うと、白くしたい部分だけを綺麗にできるでしょう。


(マスキングテープを使うこともあります。)
この作業も、最後の最後に回数を少なくして行いましょう。
消しゴムで消す作業も、実は、
少しずつ粉をすり込むことになるからです。
特に、こすって描く技法を使っている人は、
鉛筆の粉が紙に染み込んで取れなくなります。
本当の白が得られなくなるので、注意が必要です。
「練習方法」については、次の記事でで紹介したいと思います。




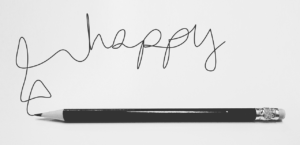
コメント